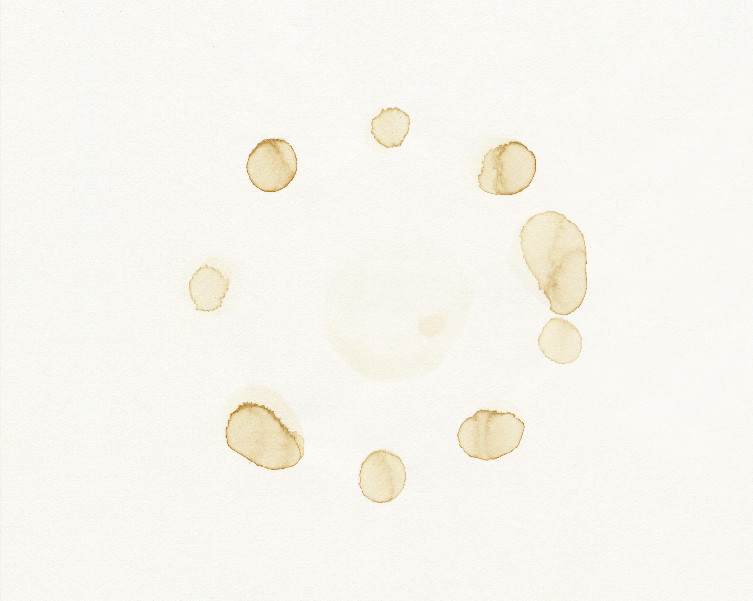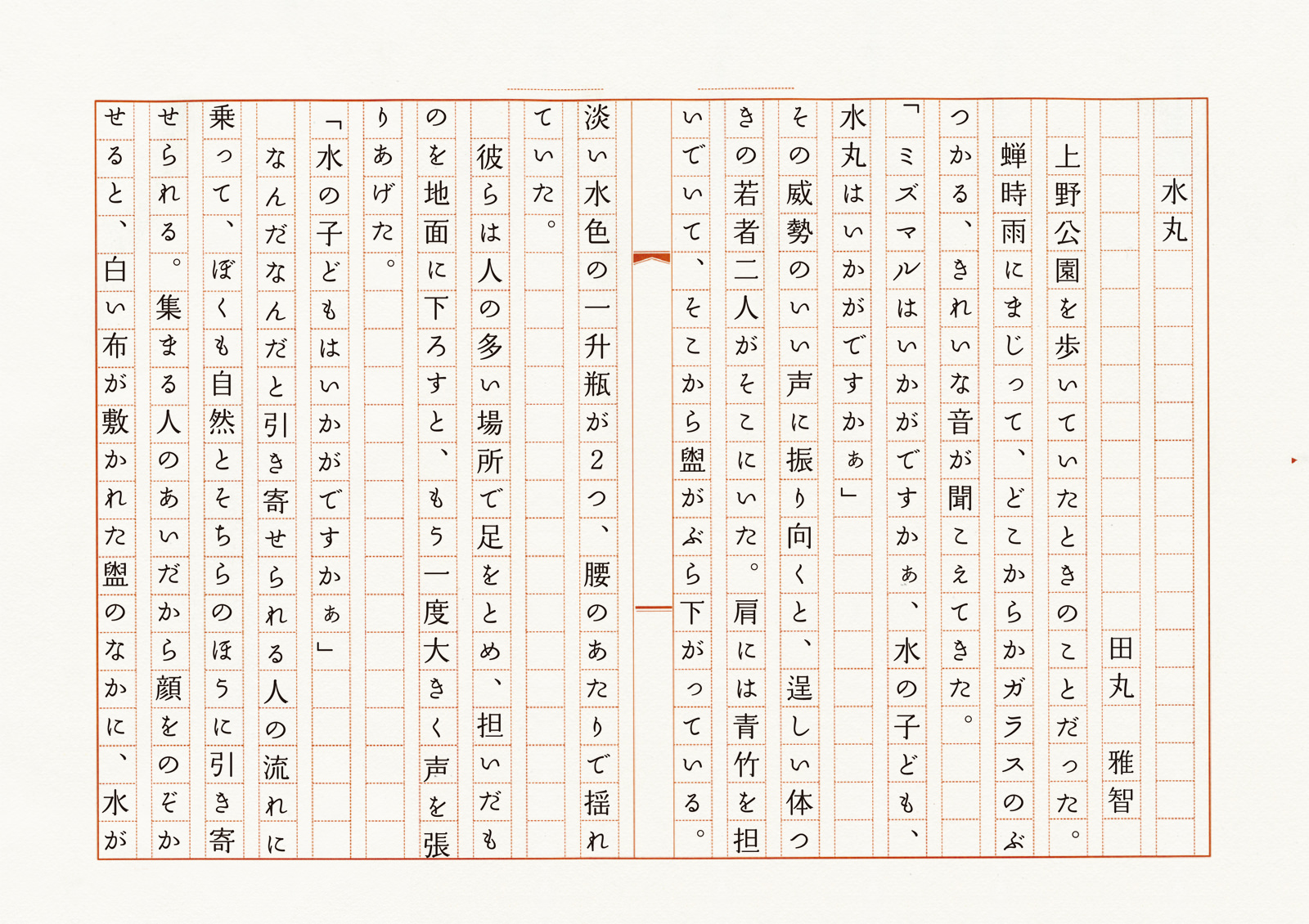「何これ!」「水?」「ぷにぷに」「気持ちぃ!」
「ねぇ、これなんなの?」
一言でうまく答えられません。
触ってもらうまでは、その気持ちよさや、
全く新しい水の感覚もうまく伝えられません。
でも、確かに僕らは「真」を伝えることができた、
と手応えがありました。
できることなら実際に触ってもらって、
自分の中の水丸を確かめてほしい。
実際に触ってもらうまではうまく捉えきれないから、
そして僕らが確かめている水丸もまた一部でしかないから、
この捉えきれない真に迫るために、小さな真の集合体でもって
水丸の正体をあぶり出してやろうじゃないか、という企画
がスタートしました。
mizumaru primal , つまり水丸の原始を探る旅が始まります。